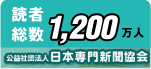自治日報 第4333号
2025年10月6日発行
■本号の主な内容
▽「公務のブランディング」推進(人事院)
人事院は、国家公務員という仕事のブランディングを人材確保の観点から戦略的に行うため、「公務のブランディング」を推進する。不服・苦情などへの対応の充実のほか、コンピューターを利用した「CBT方式」の導入を始めとした採用試験の見直しの検討にも着手。これら関連する経費などを2026年度予算・組織定員要求に盛り込んだ。(1面、続きは本紙で)
▽行政通則法的観点からAI利活用を調査(総務省研究会)
総務省の「行政通則法的観点からのAI利活用調査研究会」(座長・大屋雄裕慶應義塾大教授)は、さらなるAI利活用の進展を前提に、国民の権利利益や行政の公正性・透明性との関係で想定されるリスクや留意点への対応を、中間整理としてまとめた。AIの誤った利活用により権利利益・公正性・透明性を損なうことがないよう、利活用の指針・留意点を「ガイドライン(ソフトロー)」として策定するよう提言した。(1面、続きは本紙で)
▽概算要求締め切り前に総務省と中核市市長会が懇談会(余滴)
8月の2026年度予算概算要求締め切りを前に、総務省と中核市市長会との懇談会が開かれた。同会は、自治体情報システム標準化後の運用経費問題を真っ先に取り上げ、運用経費の増大分は国の責任で財政措置を講じるよう要請。出席した村上誠一郎総務相は「総務省としてもこの問題は非常に大きな課題と認識している」と述べ、デジタル庁で「総合的な対策」に基づき財政措置のあり方を検討していると説明した。なお、デジタル庁の概算要求では「事項要求」とされており、年末の予算編成過程で詳細を詰める(1面、続きは本紙で)
▽「地域おこし協力隊2.0」へ制度改善を(地域活性化センター・椎川氏)
地域活性化センターはこのほど、設立40周年を記念して「地方創生フォーラム」を都内で開いた。前理事長で特別顧問の椎川忍氏が講演し、地域おこし協力隊について「さらに制度の飛躍的発展を期待している」と強調。その上で、石破政権の看板政策「地方創生2.0」と絡め、「地域おこし協力隊2.0」に向けて制度を改善していく必要があるとの認識を示した。(2面、続きは本紙で)
▽【自治の現場にズームイン】「社会的インパクト・マネジメント」でシンポ開催(明治大公共政策大学院)
明治大学公共政策大学院は9月28日、都内でシンポジウムを開いた。一般財団法人「社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ」の今田克司代表理事が基調講演し、地域の課題解決に向けて、企業や行政、非営利組織などが「協業」する取り組みが見られると説明。その上で、「社会的インパクトの可視化や測定をすることによって、事業運営していこうとする規範が育ちつつある」と話した。(2面、続きは本紙で)
▽「決算」でフォローアップセミナー(LM推進連盟)
地方議員の有志らでつくる「ローカル・マニフェスト(LM)推進連盟」は10月31日、決算フォローアップセミナー「決算を予算に活かすには~令和6年度決算審議を経て~」を開催する。会場とオンライン参加を併用して実施する。(3面、続きは本紙で)
※セミナーの申し込みはこちらから
このほか、地方自治に関するニュースを独自に取材し、お届けしています。
購読やバックナンバーをご検討の方は、購読の申込みをご覧ください。