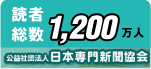自治日報 第4302号
2025年3月3日発行
■本号の主な内容
▽持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会の下に二つのWG(総務省)
総務省の「持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会」の下に二つのワーキンググループが設置された。一つは大都市特有の行政課題への対応方策を検討。いわゆる「特別市」に関する課題整理なども行い、夏頃までに論点をまとめる。もう一つは自治体でのAI利用に関する課題を議論。効率化が見込める業務や留意事項を報告書にまとめ、自治体向けガイドブックなどに反映させる予定だ。(1面、続きは本紙で)
▽アクセス確保策必要(中教審答申)
急速な少子化進行を踏まえた大学など高等教育のあり方について、中央教育審議会(文部科学相の諮問機関)は2月21日、阿部俊子文科相に答申した。特に地方を念頭に、地理的観点からの「アクセス」確保策が必要と提起。自治体などが参画する協議体を構築し、国が後方支援するよう求めた。(1面、続きは本紙で)
▽総務省の過疎問題懇談会で「集落支援員」巡り検討(余滴)
総務省の過疎問題懇談会(座長・小田切徳美明治大教授)で、「集落支援員」を巡り検討が進められている。集落支援員が担う機能を改めて整理するとともに、継続的な担い手を確保するための研修のあり方や法人・団体に属する人材の積極的な活用などが研究テーマ。既に専任の集落支援員を設置する自治体へのアンケート調査を実施済みで、担い手確保の観点では、都道府県の役割が大きいことも明らかになってきているようだ(1面、続きは本紙で)
▽「ゼブラ企業」育成へ20カ所で実証事業(中小企業庁)
社会的課題の解決と経済成長の両立を目指す「ゼブラ企業」が、地域の新たな担い手として注目されている。中小企業庁は、地域の課題解決を目指すゼブラ企業を「ローカルゼブラ企業」と位置付け、社会的インパクトを創出しながら、収益を確保する企業活動を支援。全国20カ所で実証事業を実施した。(2面、続きは本紙で)
▽マニフェスト大賞優良事例で研修会(LM推進連盟など)
地方議員の有志らでつくる「ローカル・マニフェスト(LM)推進連盟」などは3月29、30両日、昨年のマニフェスト大賞の優良事例を学ぶオンライン研修会「マニフェスト・アワード・コレクション」を開催する。受賞者らが、議会改革の最新事例や政策づくりのポイント、投票率向上の取り組みなどを発表する。オンライン上で参加者同士の意見交換の場も設ける。(3面、続きは本紙で)
※オンライン研修会の申し込みはこちらから
▽藤沢市議会・開成町議会の事例発表(LM推進連盟・勉強会)
地方議員の有志らでつくる「ローカル・マニフェスト(LM)推進連盟」主催の勉強会が2月7、8両日、神奈川県茅ケ崎市で開かれた。2日目は、同県藤沢市議会の有賀正義議員が講演し、全会派による「藤沢型政策検討会議」について「(政策提案の)最初のハードルを低くする、提案の受け皿としてのプラットフォームだ」と強調した。(3面、続きは本紙で)
このほか、地方自治に関するニュースを独自に取材し、お届けしています。
購読やバックナンバーをご検討の方は、購読の申込みをご覧ください。